10月13日(月祝)の「第3回 鳥取バロックアンサンブル with 赤津眞言」演奏会へ向けて赤津さんからの寄稿連載、第5回はいよいよ最終回です。
第4回では古楽奏法との出会いが書かれていましたが、最終回は、現在の赤津さんがこの演奏会にかける思いです。
『四季』はヴァイオリンがソロ楽器として活躍し始めた1600年ごろ以降今日に至るまで、曲中に詩(ソネット)が書き込まれた唯一の作品だ。勿論、曲のタイトルや各楽章にその曲のイメージとなる単語が示される例は多数見られるが、曲全体に渡ってまるで絵本のように物語が提示されているのは珍しい。
その詩自体はヴィヴァルディ本人が書いたのか否かは分かってはいないけれど、曲の各部分がどういう情景・意味を持っているのかが具体的に、直感的に分かるようになっている。
その詩(ソネット)をどの様に理解し表現するかは各奏者によって異なるのは当然で、だからこそ様々な演奏が存在しているのが面白い。学生の頃聴いていたアーヨの演奏は確かに美しい。しかしもっと人間的な自由さ、自然と共に過ごすことで感じる驚異、感嘆、喜び、絶望や怒りが表現されていても良いのではないか。
バロック・ヴァイオリンを使うことで、より人の声に近く、より直接的に表現できるし、心の中の言葉を、モダン・ヴァイオリンを使う演奏より容易に(簡単にではない)表現できるのではないかと考えている。
それは『四季』だけではなく、全ての曲に対しても、である。
鳥の鳴き声、雷の音、吹き荒ぶ風や雨、収穫の喜び、凍てつくような寒さ、そしてやがて迎える春を思う心。全ての事象から受ける気持ち、自然と発する言葉は、自身の生活に直結していて決して特別なものではない。寧ろそれこそが人生そのものなのではないだろうか。
余す所なくそれらを表現し伝えること、それが私が鳥バロとの共演で課せられた使命なのだろう。
何事も趣味良くあらんと。
Ex revelatione Dei musicae manifestabitur.(音楽の神の啓示によって、我々の音楽は表出されるだろう。)
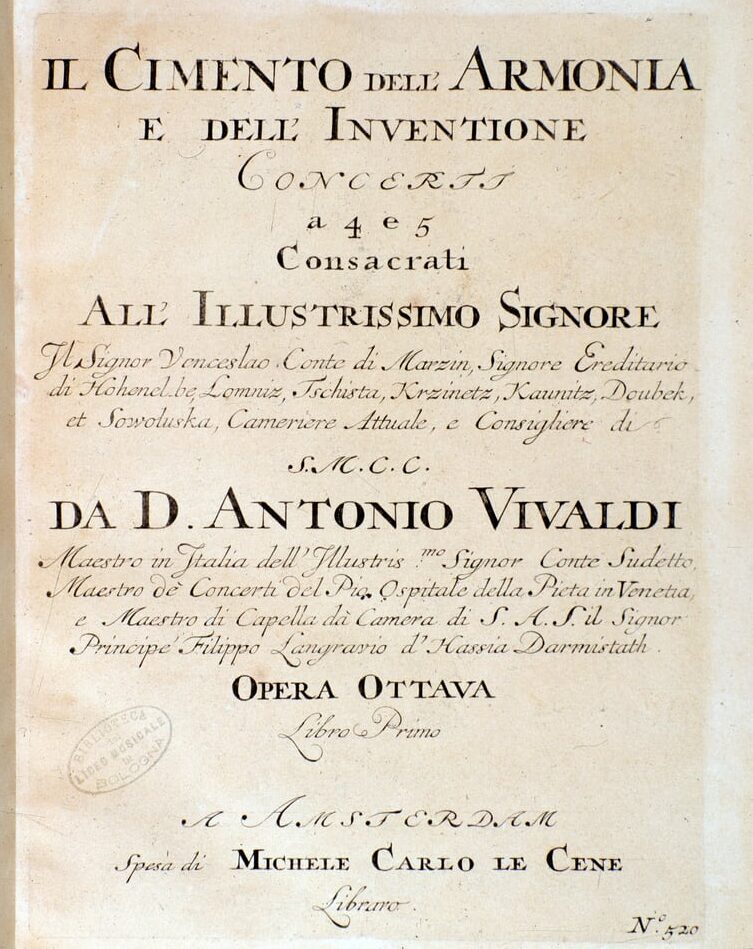

5回にわたって掲載してきた「『四季』と鳥バロ」最終回でした。こちらから全5回お読みいただけます。
「第3回 鳥取バロックアンサンブル with 赤津眞言」の情報はこちらからご覧ください
Share this content:
